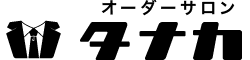昨日の日経を読んでいたら、杉山清貴さんが書いたバングラデシュのコンサートへのエッセイが掲載されていた。
中学2年の頃、バングラデシュのコンサートというスーパースターがわんさか出るコンサートがあり、そのドキュメンタリー映画が上映されるということが教室の話題になった。それはちょうど7月の期末試験の終わった日。昼前に学校がおわるやいなや霜降りブルーのパンツとグレーの開襟シャツを来たわれわれは学校帰りに伏見のヤマハの前にある名古屋東宝にかけつけた。映画館の座席に着くと、おんなじ制服をきた同級生が30人は館内にいた。それほど話題だったのだ。映画はまずラビ・シャンカールのシタールの演奏がはじまる。ラビ・シャンカールはバングラデシュのコンサートの呼びかけ人、ジョージ・ハリスンのお気に入り。奇しくもあのノラ・ジョーンズの父でもある。ジョージ・ハリスンがいいといっていたからいいに違いないと思い聞いていたが聞きなれないインド音楽で案外メロディアスだなと思いながら退屈感は否めない。眠さをこらえて待っているとお待ちかねバングラデシュのコンサートの幕が開く。ジョージ・ハリスン、ボブ・ディラン、エリック・クラプトン、レオン・ラッセルなどのすげーメンバーが一同にそろいステージにあがる。クラプトンはストラトキャスターのヘッドにタバコを挟んで演奏する。いまステージの上でタバコをすうミュージシャンっているのだろうか。ひときわ輝いていたのがインディアンのギタリスト、ジェシ・エド・デイヴィス。最後に演奏した「バングラデシュ」のリフレインが今でも耳に残っている。そんな40年以上前のことだがなにも調べずにすらすら思い出す。
ロックはカントリーミュージックと黒人音楽がハイブリッドして1950年代出来上がったがその後演奏技術、表現方法を競いあい英米を中心に発展そしてそれは世界の若者を魅了してきた。ロックの偉大な旗手のひとり、僕自身ライブに4回も行っているボブ・ディランが今月になってノーベル賞受賞しながら無視した。そんな彼にロックのこころ、いわば「反骨精神」を感じ、ちいさく拍手したくなる。ロックは間違いなくぼくらの人生の一部だった。クラシックやジャズ、邦楽あたりが今のぼくの年齢には似合うかもしれないがまだまだ成長がないのかいまだに馴染めない。いままでもこれからもノーロック、ノーライフ。
集めた大好きなグレイトフルデッドのCD。今でもデッドの音は飽きない。